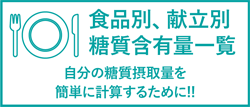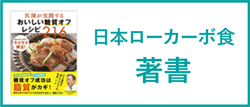血糖のホメオスタシスで忘れがちなもう一つの視点—その2
「その1」で紹介した論文の8名の著者のうち、責任著者Fineman, Mを始めとしT.K., C.B., S.S., A.B. の5名はSan Diegoの製薬会社Elcelyx Therapeuticsに所属し、Met DRは同社が開発し発売している薬品であるが、報告にDiabetes Careの編者が注目して論文に先立ち下記のコメントを同時に掲載している。
Song, R (Dept of Biol Chem and Mol Pharmacol, Harvard Med Sch, Boston, MA)
Mechanism of metoformin: A tale of two sites. Diabetes Care 2016; 39:187-189
殆どの著者の利益相反は紛れもなく、極めて胡散臭い論文の範疇に入るが、それを加味しても論文の報告には注目すべきものがあると判断し「その1」で紹介した。
糖尿病経口治療薬としてのビグアナイドの歴史は古く、中世南・東ヨーロッパでマメ科の牧草のガレガ草が糖尿病を抑える薬草として用いられていたことに遡る。ガレガ草(Galega officinalis)の有効成分はグアニンやアミノ酸から生成する強塩基性のグアニジンであるが、グアニジンは毒性も強い。1920年代になってより毒性の少ないグアニジン2分子からなる複数種のビグアナイドが合成され、それらによる血糖低下が報告されている。1950年代にビグアナイドが高血糖の治療薬として報告されたが、副作用として深刻なアシードーシスを起こしやすいことから忌避された。
しかし、1990年代になって副作用がほどほどのジメチルビグアナイドつまりメトフォルミン(Met)が経口糖尿病薬として再評価され、現在では経口治療薬の第一選択肢として定着している。加えてMetには一部のガンの発症リスクを低下させるとの少なからぬ疫学的報告が知られている。糖尿病薬としてビグアナイドの有効性が認識されるのが遅れたのは、副作用の問題に加え、1921年のインスリン発見のインパクトが余りにも大きかったことによるのではないか。
現在ではMetによる血糖降下の原因として主に肝臓における糖新生の抑制が明らかになっているが、その作用機作については「その1」で触れたように諸説(a ~ d)がある。いずれも循環血に乗って臓器に運ばれたMetの示す作用である。近年では (d)の血中Metが肝臓で細胞に取り込まれ細胞質のNADHをミトコンドリア内に搬入するミトコンドリア膜上のシャトル酵素(mGPDH)を阻害する結果、細胞質NADH濃度が上昇して(乳酸とグリセロールからグルコースを生成する)糖新生を阻害するという可能性が有力視されている。
Met DR、Met IRを用いる今回の報告は、Metが回腸のL-細胞に作用してインクレチンの分泌促進することが血糖低下の主因 (~70%)であることを示唆し、グルカゴン作用(グリセロール経路の糖新生を促進、グリコーゲンの加水分解を促進)の抑制が主要な血糖低下に繋がる可能性を示唆している点で興味深い。DPP-4阻害剤もインクレチンの分解を抑制して血糖降下を招くが、Metとの併用が効果的に血糖値を低下させるという臨床経験とも合致する。
Metが肝臓に直接作用して起こす血糖値の低下は全体の ~30% 程度と推定され、 (d) のmGPDHの阻害によるもので、乳酸及びグリセロール経由の糖新生が共に阻害されるため同時に乳酸の血中濃度が上昇してアシドーシスのリスクが高まる。また、Met効果の(a) 、(c)及び (d)も 細胞内シグナルの伝達に関わるAMP依存のタンパク質リン酸化酵素AMPKsの活性化に繋がり細胞分裂を抑制するので、報じられているMetのもう一つの効果である発ガンの抑制に関係する可能性が高い。糖尿病患者のガン発症リスクは健常人にくらべ高く、その意味でもMet DRとMet IR or XRの併用はT2DM患者にとって有意義かもしれない。また、Metの顕著な副作用である下痢または便秘を伴う胃腸障害はMetが腸管粘膜細胞に異常な高濃度で蓄積することと関連している可能性がある。
肝臓はヒトが絶対的に必要とするグルコースの量135gの全てを糖新生により合成できる(田川 改訂版からだの生化学 2008)。このことは、糖新生は食事と並んで血糖のホメオスタシス(恒常性維持)にとって巨大な血糖供給代謝を担い、その調節はインスリン関与の血糖消費代謝に勝るとも劣らない役割を果たしていると考えるのが合理的である。
近年、血糖のホメオスタシスにおける糖新生(グリコーゲンの分解を含む)の役割に注目した研究報告を目にする機会が増えたが、今回の報告から、生理学の父と云われるClaude Bernardが1848年に栄養状態に拘わらず血糖値を保つことが出来る肝臓における強大な糖生成(糖新生)機構を発見した(三浦訳 実験医学序説 岩波文庫)ことの現代的な意義の再評価が糖尿病の病理・治療研究のさらなる進展に求められているように評者には思われる。
グルカゴン、インスリン、ソマトスタチン等の糖代謝に関わるホルモンの分泌細胞(α、β、δ細胞)はすべて膵臓にあり、互に影響し合って血糖の調節に関与していることは既に明らかになっている。各分泌細胞は膵臓の小さなランゲルハンス島内にモザイク状かつ密にまとまって配置されているという解剖学的事実も、血糖の供給代謝と消費代謝の密接なバランス調節のメカニズムの理解が血糖のホメオスタシスを考える上で基本であることを強く示唆している。